うだるような暑さが続く日本の夏。人間だけでなく、庭の植物たちにとっても過酷な季節です。
この記事では、夏の過酷な環境から大切な植物を守るためのマルチングについて、その効果から、コストゼロでできる方法、具体的な実践のコツまで、私の実体験を交えながら詳しく解説していきます。今年の夏こそ、マルチングで植物にとって快適な環境を整え、元気な庭で夏を乗り切りましょう!
むき出しの土にうけるダメージ
むき出しの土に直接夏の猛烈な日差しが当たるとどうなるでしょう?私が感じるダメージは以下の二つ。
水分の急激な蒸発
気温と地温が高いと、土の中の水分はどんどん蒸発していきます。せっかく水やりをしても、夕方にはからっからに乾燥して、植物は水不足に。
土がカチカチになる
強い日差しで土の表面が急激に乾燥すると、地表に硬い膜ができてカチカチになります。専門的には「クラスト形成」というそうです。こうなると、水やりの水が土の中に浸透しにくくなり、表面を流れていくだけになってしまいます。特に鉢管理でその状態を感じることがあります。
対策は「マルチング」
マルチングとは、植物の株元の土の表面(地表面)を、有機物やビニールなどで覆う園芸手法のことです。
マルチングがなぜ夏の猛暑対策に絶大な効果を発揮するのか、その仕組みは非常にシンプルです。
- 直射日光をシャットアウト: マルチング材が物理的に日光を遮ることで、土に直接熱が伝わるのを防ぎます。これにより、地温の急激な上昇を効果的に抑制できます。
- 断熱材としての効果: マルチング材が作る層は、空気を含んだ断熱材のような役割を果たします。外気の熱が土に伝わりにくくなるため、一日を通して地温を安定させることができるのです。
実際に、マルチングをした場所としていない場所の地温を測ると、夏場では10℃以上の差が出ることも珍しくありません。この「10℃の差」が、植物の生死を分けると言っても過言ではないのです。
我が家の秘策!コストゼロでできる「自家製ウッドチップ」マルチング
我が家では、「自宅で剪定した木の枝を細かくしたもの」を自家製ウッドチップと呼び、マルチング材として使っています。こちらの【もう捨てない!】庭木の剪定枝を100%活用するアイデア術|ユーカリ・シマトネリコ編でも剪定枝の活用方法を紹介しています。
【自家製ウッドチップの作り方】
1. 剪定した枝を、1〜2週間ほど雨の当たらない場所で乾燥させます。生木よりも乾燥させた方が作業しやすくなります。
2. 太い枝からノコギリで細い枝を取り除きます。細い枝を丈夫な剪定ばさみで、5cm程度の長さにカットしていきます。

【自家製ウッドチップのメリット】
- コストがかからない
- 通気性を適度に保つ
- 風で飛ばされにくい
- 土ではないので雑草防止効果がある
- 古くなったらそのまま土に混ぜていい
- ゴミも減らせる
唯一感じる【自家製ウッドチップのデメリット】としては「手間がかかる」ということです。この手間が無理という方には、次に紹介する市販の資材をおすすめします。

手軽に始めたい人へ!おすすめのマルチング材
「剪定枝がない」「作る時間がない」という方にも、おすすめのマルチング材をご紹介します。
1. バークたい肥(樹皮たい肥)
樹皮(バーク)を発酵させて作ったたい肥です。黒っぽい色合いで見た目も良く、土の上に敷くと庭全体が引き締まった印象になります。土壌改良効果も高く、マルチング材としての役目を終えた後はそのまま土にすき込むことができるので非常に便利です。
2. 腐葉土
落ち葉を発酵させて作った土壌改良材の定番です。保水性・保肥性が高く、マルチングに使うことで土の乾燥を効果的に防ぎます。こちらも最終的には土に還るので無駄がありません。ただし、バークたい肥に比べて目が細かく風で飛びやすいことや、製品によっては未熟で虫が湧きやすい場合もあるので、完熟のものを選ぶようにしましょう。
3.雑草や草花の切り戻したもの
樹木の剪定枝はなかなかいつでもありませんが、ガーデニングをしている方なら、抜いた雑草や、草花類を切り戻しした残渣などは手軽に集められるのではないでしょうか。そういったものも十分マルチング材として活躍してくれます。ただし、地下茎で増える雑草は取り除きましょう。雑草を増やしかねません。また、ネモフィラのように水分が多い植物も腐ってしまう原因になるので向きません。稲わらのように硬くてカサカサになるものが向いています。
これらの有機マルチング材は、地温抑制だけでなく、土の中の微生物の活動を活発にし、長期的に見て植物が育ちやすい「ふかふかの土」を作る手助けをしてくれます。
まとめ:今年の夏は「マルチング」で快適なガーデニングを
夏の猛暑は、ガーデナーにとっても植物にとっても試練の時ですね。大切な植物たちが元気に夏を越せるよう、ぜひ今年の夏はマルチングに挑戦してみてください。
最後までお読み下さりありがとうございました。
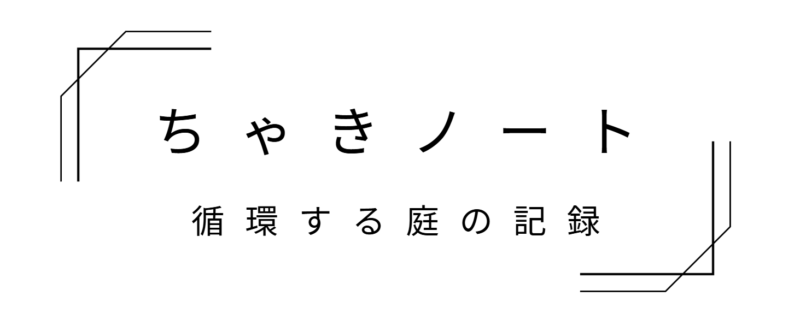



コメント