「ビオラの種取りといえば、お茶パックや排水口ネットを被せるのが一般的ですよね。でも、せっかく綺麗に咲いている花壇が、ネットだらけでゴミ捨て場みたいになるのは嫌じゃないですか?
実は、毎日観察していると『今日弾ける!』というサインがあります。これを知っていれば、ネット不要でスマートに種取りができるんです。
パンジー・ビオラの種取りの時期
パンジー・ビオラの種取りに適した時期はずばり春です。
パンジー・ビオラの販売は年々早まっており、早ければ9月からでも苗が出回っています。
ですので花期は、秋から春までの長期間にわたります。
しかし、秋はまだ苗も小さく種を付けるには株に負担をかけてしまいます。
冬は成長が遅くなり、種もなかなか熟しません。品種によるかもしれませんが種自体ができにくいように感じます。
春になれば、成長も進み、花は次々に咲いてきます。
株自体も大きくなり体力がついていますので、花を咲かせながら種を付けさせることができます。
パンジー・ビオラの種取りの方法
4月になったら種を付けさせる
私はわざわざ人の手で受粉は行っていません。蝶や蜂などによる自然受粉に任せています。
人工授粉も行ったことがあるのですが、難しく、管理がかなり手間でした。
一番簡単な方法は、花ガラを摘みながら、種ができているかどうか確認することです。
花びらがしおれた頃に花ガラを摘みますが、その時にガクのあたりをつまんでみてください。
種ができているものは、ゴロっと硬い感触があります。膨らんだ部分を残してしおれた花びらだけを取り除きましょう。
硬くなっていないものは種ができていないのでそのまま摘み取ってOKです。
花ガラ摘みは、花をたくさん咲かせるために欠かせない作業ですが、完ぺきにする必要はありません。
取り残した花が種を付けていることもあるんです。
手を抜いたことで来年の楽しみができるなんて最高ですね!
袋いらず!種を取る「ベストなタイミング」の見極め方
ここが最も重要なポイントです。
一般的には、弾けるのを防ぐために「お茶パック」や「ネット」を被せる方法が紹介されています。
しかし、私はあえて何も被せずに収穫しています。
理由はシンプルで、せっかく綺麗に咲いているお花にお茶パックが被さっていると、観賞価値が下がってしまうから(見た目がイマイチ…)です。
また、実際にお茶パックを試したこともありますが、うまく装着できずに隙間からこぼれ落ちてしまう失敗もありました。
実は、種が熟すプロセスと「サイン」さえ知っていれば、お茶パックなしでも、弾ける直前にサッと収穫することができるんです。
種が熟していく過程は以下の3ステップです。

- 初期:種ができると最初は種袋は下を向いたままで徐々に膨らむ(画像黄色の〇印)。
- 中期:種が熟してくると種袋は上向きになっていく(画像オレンジの〇印)。
- 完熟: 種が完熟すると種袋がはじけて種が飛ぶ(画像赤い〇印)。
私のおすすめは、「2」の段階での収穫です。
この時期に採っても種自体は十分に熟しているため、発芽率には全く問題ありません。これなら、お茶パックで庭の景観を損ねることなく、美味しいところ取りができます。
失敗しない見極めのコツ
「2(上を向く)」の中でも、さらに詳しいベストタイミングがあります。
種袋が上を向いた後、数日から1週間程度観察していると、種の周りにうっすらと「茶色い筋」が見えてきます。
これが「もうすぐ開きますよ」という合図です。
この「茶色い筋」が見えたら、迷わず収穫しましょう!
(※私の地域では、4月に種の出来はじめを確認し、実際にこのタイミングで取れたのは5月上旬でした)
種を取った後は

上の画像はうっすら茶色い筋ができたタイミングで収穫したものです。
ここから乾燥すると自然とはじけるので、乾燥しやすいようにガクを取って紙袋に入れて保存します。

紙袋に入れておいた翌日、もうはじけて中の種が出てきていました。
種の色は濃い茶色から黒で、十分発芽してくれそうです。(室内まきでしっかり発芽確認済み)
保管場所は「室温」か「冷蔵庫」か?
はじけた種は、そのまま紙袋に入れて室温で保存することも可能です。
エアコンの効いた涼しい室内で管理できるのであれば、8月下旬からの種まきシーズンまでそのままでも問題ありません。
ただし、私はより確実に発芽率をキープするために、1週間ほどしっかり乾燥させた後は「冷蔵庫の野菜室」へ移動させることをおすすめしています。
理由は2つあります。
- 日本の夏は高温多湿なので、室温だと種が弱ってしまうリスクがあるから。
- 「寒さ」を経験させることで、種まき後の発芽が揃いやすくなるから。
特に2つ目の「寒さを経験させる」というのは、ビオラの種まきを成功させ管理を楽にするための重要なテクニックでもあります。なぜ冷蔵庫に入れるだけ管理が楽になるのか?その詳しいメカニズムや具体的な手順については、別の記事でじっくり解説しています。
冷蔵庫保管の「あの不安」を解消する方法
ただ、冷蔵庫に入れるとなると、一つだけ気になることがありませんか?
そう、「土いじりをした後の種を、食材と一緒に入れる抵抗感」です。
「もし目に見えない小さな虫やダニがついていたら…」なんて考えると、そのまま紙袋で野菜室に入れるのはちょっと怖いですよね。
そこで私は、必ずジップロックなどの密閉袋や密閉容器に入れてから冷蔵庫に入れています。これなら衛生的にも安心です。
でも、ここで新たな心配が…。
「もし種の乾燥が不十分だったら、密閉された袋の中で湿気がこもってカビるんじゃ…?」
「冷蔵庫から出した時の温度差で、袋の中に結露ができたらどうしよう…?」
密閉すれば虫は防げるけど、今度はカビのリスクが高まるというジレンマ。
この「虫もカビもどっちも防ぎたい!」という悩みを解決するために私が使っているのが、シリカゲル(乾燥剤)です。
使い方は簡単。密閉袋の中に種と一緒にポンと入れておくだけ。
これなら、万が一乾燥が甘くてもシリカゲルが湿気を吸ってくれますし、結露対策にもなります。
「虫対策の密閉」+「カビ対策の乾燥」。このダブル対策なら、安心して野菜室に入れておけますよ。
早いタイミングでとった場合
試しに、下を向いた状態の種を採取してみました。

上を向いた時に採取した種よりも青みがかっていて、茶色い筋もまだでていません。
紙袋に保存した翌日にはじけていました。

色は上を向いた状態で収穫した種よりも薄いですね。
このまましっかり乾かせば何とかまけるか…。8月にまいてみて、発芽率を確認する予定です。
種取りで気づいたこと
パンジー・ビオラの種取りをし始めて気づいたことがあります。
一つ目は、種の取りやすさに色や花形が関係しているのではないかということです。
原種に近い紫はたくましく、種もどんどんできますが、品種改良されていて凝った花色・花形のものは種が付きにくく感じます。
品種改良は育種家さんの努力の賜物ですね。
・種がとりにくい…赤・黄・水色・ベイン・フリル
・種がとりやすい…原種に近い紫
二つ目は、親と同じものが咲くとは限らないということです。
これも自然受粉なら当然といえば当然ですが…。
私は最初に「よく咲くすみれ」という種からまき始め、毎年種取りをしたものから咲かせていますが、時折これまでに全然見たことない花色の組み合わせが出てくることがあります。
こういう宝くじみたいな楽しみが植物の世界にはあるなとつくづく感じさせられます。
私は、サカタのタネ「よく咲くすみれミックス」はこちら。本当に良く咲きます!
自家採種を繰り返した記録は、こちらで記事にしています。
皆様も、植物の沼にはまってみてはいかがですか?
最後までお読みくださりありがとうございました。
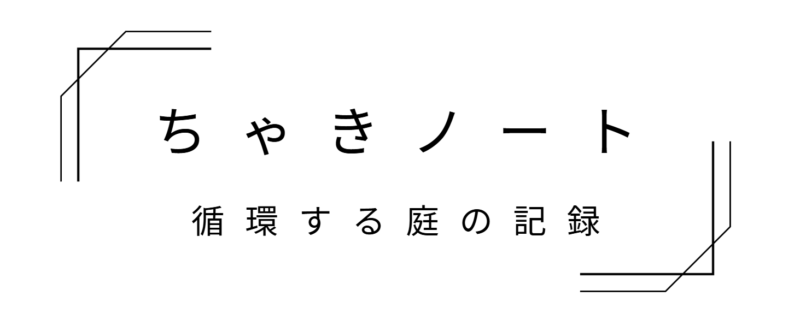







コメント