ここではオダマキの紹介と、実際に育てている西洋オダマキの種まきから開花の様子を写真付きで解説します。
トップの画像は「ウインキーダブルブルーホワイト」八重咲きの西洋オダマキです。
オダマキとは
オダマキには、日本原産のミヤマオダマキとヨーロッパや北米原産の西洋オダマキ(アキレギア)があります。掛け合わせしやすい性質であり、大輪咲きや八重咲、白・青系・赤系など色幅も広く、多くの園芸品種があります。丈夫で初心者さんでも育てやすい宿根草です。
少しうつむき加減で咲くところが控えめで、クリスマスローズと雰囲気が似ています。
花の時期:5月~6月
花色 :白・青・紫・ピンク・赤・オレンジ・黄・茶・黒
草丈 :30~50cm
花言葉 :「必ず手に入れる」「勝利への決意」
その他 :直根性・好光性種子
オダマキの種まき
種まきの基本情報
まき時 :9月から10月(暖地)
発芽温度:15~20℃
覆土 :好光性種子のため、薄く覆土。
発芽まで:約2~3週間
我が家での種まきの方法
- まき床の準備
オダマキは直根性なので移植の負担を減らすため、セルトレイに用土を入れ、水をかけます。もちろん種まき専用用土や新品の培養土がいいのですが、オダマキは、零れ種からでも発芽する草花としてよく紹介されています。我が家では使い古しの土を使いましたがよく発芽してくれました。 - 種をまく
用土が十分に湿ったら、種をまきます。オダマキの種はとても小さく、好光性種子でもあります。風にとばされないように薄く覆土し、優しく霧吹きなどで水やりをします。

オダマキの育て方
育て方の基本情報
植付け:2~3月、9~10月
環境 :水はけのよい土壌、日向から半日蔭
耐寒性:強い
耐暑性:普通
我が家での育て方
- ポット上げ
発芽後、本葉が2~3枚になったころポット上げしました。ポット上げ1~2週間は半日蔭で慣らしました。 - 庭に移植
3月、オダマキは直根性なのであまり大きく生長しないうちに庭へ移植しました。12月に下の画像よりももっと小さな苗を植え付けたこともありますが、春になっても大きくならず小さいままでした。日当たりの問題もあったかもしれません。
場所は我が家と隣の家の間の通路のようなところへ。オダマキは耐暑性が強くないということで日2~3時間日が当たる場所を選びました。元肥として根元にマグァンプKを与えました。 - 開花までの管理
オダマキは、じめじめした環境を好みません。移植後しっかり根付いた後は、水やりはほとんどしていません。真夏の晴天が続いた時だけ午前中に水やりをします。肥料もやっていません。 - 1回目の開花
移植したその年の春は花を咲かせることはなく翌年の春に花を咲かせてくれました。ほぼ無施肥ですが花数も多く、長く楽しませてくれました。 - 種の採取
たくさんの種を付けました。一つの花から数えきれないくらいの種が取れます。コップ状の種袋の中にさらさらとした小さな種がたくさん詰まっています。口が開いていて下に向けると落ちてしまうので気を付けて採取しましょう。
オダマキの種取りについてはオダマキの種取り入門 タイミングを見極める2つの方法とは?で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。

オダマキの四季
春
1年目の株
下の画像はポットで冬越しした4月の様子です。上の画像(ポット上げ後12月)の4か月後のものです。冬にはいったん小さくなった株も芽吹きにより再び成長しています。

また、12月にポット上げし、4月上旬に庭に植え付けたものでも、花をつけてくれた子もいました。

2年目の株:特徴的なクローバーのような新しい葉っぱが芽吹いてきます。次に花茎がすっと伸びてきてその先につぼみを付け開花します。
夏
オダマキは耐暑性があまり強くありませんが、半日陰で夏を越せます。葉っぱはふさふさとしたままです。
残念ながら、オダマキも夏越しができず、寿命を迎えてしまうこともあります。その様子をこちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
【衝撃】宿根草のはずが…?私が育てたオダマキが「突然消えた」謎を徹底解明!
秋
気温が低くなってくると外側の葉っぱから枯れていき、株が一回り小さくなります。
紅葉はあまり見られません。
冬
少しずつ葉っぱが枯れていくので、古葉を取り除いてあげます。イチゴの古葉とりと同じ要領で、古葉を下に押すようにするとスムーズにとれます。

最後に
オダマキは、あまりホームセンターなどで販売しているのを見かけませんが、可憐で育てやすい宿根草です。
株が古くなると咲かなくなる、枯れてしまうという話もありますが、我が家では3年目の株も咲いてくれました。古葉とり以外ノーメンテナンスです。
交雑しやすい性質でもあるため、いくつかの品種を育てて種から育ててみるのも楽しみがありますね。
まだオダマキを育てたことがない方は、ぜひ育ててみてください!
最後までお読み下さりありがとうございました。
こちらから、オダマキの種や苗を購入することができます。
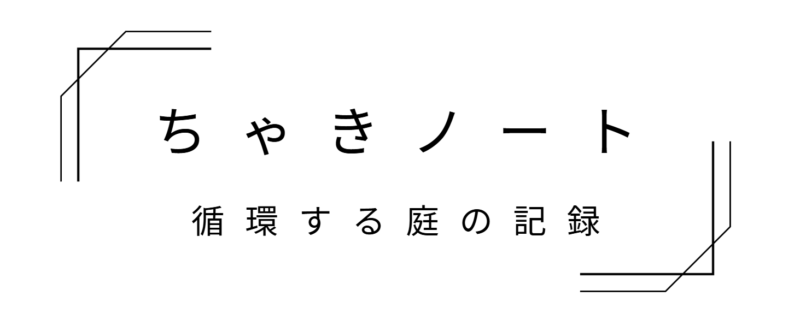




コメント