厳しい暑さが続いた今年の夏、庭では一つの変化が起きていました。一年草として育てているアリッサムの一株が、例年とは異なり、夏を越して9月に再び花を咲かせたのです。本来、アリッサムは高温多湿を苦手とし、日本の夏を乗り切るのは難しいとされています。
この記事では、なぜアリッサムが夏越しできたのか、その理由を庭の環境変化から考察します。そして、その背景にある「シェードツリー」の重要性と、庭の資源を活かす循環型の庭づくりについて、自身の経験をもとに記録します。
夏の終わりに見た、嬉しい発見
毎年晩秋に、パンビオとともにアリッサムの苗を植えています。早ければ冬前から初夏にかけて白い絨毯のように広がり、甘い香りを漂わせるアリッサムは、庭に欠かせない植物の一つです。一年草であるため、花期が終わると自然に枯れていくのが通例です。私はそのサイクルを尊重し、枯れた後もすぐに片付けず、種がこぼれたり、有機物として土に還ったりするまで、そのままの状態で見守るようにしています。
しかし、今年は様子が違いました。9月に入り、夏の暑さが一段落した頃、庭の一角で再びアリッサムの白い花が咲いていることに気づきました。その周りでは、夏の暑さに強いニチニチソウやセンニチコウがまだ元気に花をつけています。涼しい気候を好むアリッサムと、夏の草花が同時に咲いている光景は、これまでの私の庭では見られなかったものです。

なぜ、この一株だけが過酷な夏を生き延びることができたのか。その原因を探るため、株が植えられている場所の環境を改めて観察することにしました。
夏越しの要因は「庭木が作った日陰」
アリッサムが植えられていたのは、南西向きの庭の、建物の壁際に当たる場所です。この場所は日当たりが非常に良く、特に午後の西日が強く当たります。コンクリートの基礎からの照り返しも強く、夏場は植物にとって非常に厳しい環境となります。
そんな場所で夏越しができた直接的な要因は、数年前に植えた庭木が作り出す「日陰」にあると考えられます。観察してみると、ちょうどアリッサムの株元に、昼過ぎから西日が傾く時間帯にかけて、木漏れ日が落ちるようになっていました。この適度な日陰が、強すぎる直射日光を遮り、地温の異常な上昇を抑制したことで、アリッサムが夏の間、体力を消耗しすぎずに済んだのでしょう。
この日陰を作ってくれていた庭木は、シンボルツリーとしても人気の高い「シマトネリコ」です。
こぼれ種から育てたシェードツリー
このシマトネリコは、園芸店で購入したものではありません。もともと玄関前に植えていた親株からこぼれた種が、庭のあちこちで発芽したものです。シマトネリコは非常に生命力が強く、条件が合うと驚くほど多くの実生苗(こぼれ種から発芽した苗)が育ちます。
通常であれば雑草として扱われることも多いこの実生苗を、当時はかわいくて集めては、ポットで育てていました。そして背丈が50cmほどになったころ、夏の西日が厳しい南西の庭のフェンス沿いに、それらの苗を数本まとめて植え付けてみました。将来的に成長し、夏の強い日差しを和らげるシェードツリー(日陰を作る木)としての役割を担ってくれることを期待してのことでした。
その苗木が年月を経て2mを超える高さにまで成長し、結果として、庭の環境を大きく変える存在となっていました。
玄関前の親木から生まれた命が、庭の別の場所で新たな役割を得て、他の植物の生育環境を改善する。これは、私が目指している「庭の資源を循環させる庭づくり」が、意図せずして一つの形になった事例でした。
シェードツリーが庭と暮らしにもたらす効果
今回のアリッサムの件をきっかけに、シェードツリーがもたらす効果を改めて認識することになりました。その効果は、特定の植物を守るだけでなく、庭全体、さらには室内の環境にまで及んでいます。
1. 植物の生育環境の改善
最も直接的な効果は、植物が夏を越しやすい環境が作られることです。木陰は高温と乾燥を嫌う植物にとっての避難場所となります。直射日光による葉焼けを防ぎ、土壌の水分蒸発を緩やかにすることで、植物のストレスを軽減します。これにより、これまで育てることが難しかった半日陰を好む植物なども、庭の植栽計画に取り入れられるようになり、多様性が生まれます。
2. 水やりの負担軽減
日陰ができることで土壌の保湿性が高まり、水やりの頻度を減らすことができます。特に猛暑期には朝夕2回の水やりが必要になることもありますが、木陰のエリアは土の乾きが穏やかになるため、管理の手間が省けます。これは、節水という観点からも有益です。
3. 室内環境への影響と省エネルギー
シェードツリーの効果は庭の中だけにとどまりません。我が家の南西の庭にはリビングの掃き出し窓が二つ面しており、例年の夏は午後の日差しで窓ガラスが高温になっていました。その熱が室内に伝わり、冷房効率の低下を感じることも少なくありませんでした。
しかし、シマトネリコが成長した今年は、窓ガラスの温度上昇が明らかに緩和されていました。樹木の葉が天然のブラインドのように日差しを遮り、室温の上昇を抑えてくれたのです。これは体感的な涼しさだけでなく、冷房の使用を抑制し、結果的にエネルギー消費を削減することにも繋がります。庭木を植えることが、快適な室内環境の創出と省エネルギーに貢献する、という事実を実感しました。
庭の循環を意識した庭づくり
今回の経験は、庭にあるものを無駄にせず、活かしていくことの価値を教えてくれました。
- こぼれ種から発芽した苗を、新たな役割を持つ庭木として育てる。
- 成長した庭木が日陰を作り、他の植物が育つ環境を整える。
- その環境下で、一年草が夏を越し、再び花を咲かせる。
これらはたまたま私のもったいない精神から生まれた棚ぼた効果ではありますが、結果的に外部から新しい資材を持ち込むのではなく、庭の内部で生まれたものを活用することで成り立つという循環がもたらされました。
花がらを摘まずに残しておくこと、枯れた草花をすぐに処分せず土に還る時間を与えること。こうした一つ一つの小さな選択が、思いがけず庭全体の生態系を豊かにしてくれました。自然の力に感謝です。
もったいないなぁとか、園芸本では教えられた通りにしなかったらどうなるんだろうとか、そんな思い付きで行動してみるのも新しい発見につながるかもしれませんね。
まとめ:これからの庭づくりと庭木の役割
年々、夏の暑さが厳しさを増す中で、庭づくりにおける暑さ対策は避けて通れない課題です。その有効な手段の一つとして、シェードツリーを計画的に配置することの重要性は、今後ますます高まっていきそうですね。
一本の木は、ただそこに在るだけでなく、日差しを和らげ、土の潤いを保ち、多様な植物の生育を助け、さらには私たちの暮らしにも快適さをもたらします。
一株のアリッサムが見せてくれた小さな変化は、庭という空間が持つ、植物と環境の相互作用の奥深さを示唆するものでした。こぼれ種から育ったシマトネリコが作った日陰という、ささやかながらも確かな恩恵。これからも、こうした庭の中で起こる静かな循環に目を向けながら、時間をかけてゆっくりと、持続可能な庭を育んでいきたいと考えています。皆様もご自身なりのガーデニングをぜひ楽しんでみてください。
こちらの樹木を庭に植える時の注意点についても、よろしければご覧ください。
最後までお読み下さりありがとうございました。
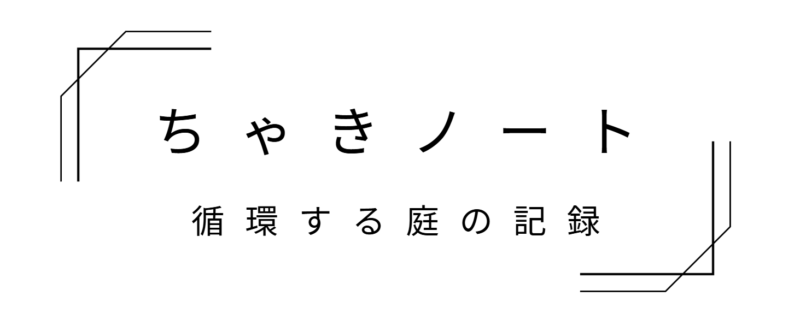



コメント